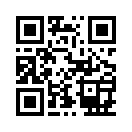2008年01月20日
三十三間堂(前編)
ついこの間の1月13日に三十三間堂にて全国の遠的大会が行われました。
そうです、すでに時は20日を迎えており実際に遠的を行ったのは先週の話です。
三十三間堂といえば堂射、いわゆる通し矢が有名です。この通し矢のゆかりで今回の遠的大会が行われているわけですが、通し矢そのものがいったいどういったものであったのかご存知でしょうか。
通し矢というのは三十三間堂の軒下をその名の通り射通す競技であって、120Mあります。ちなみに今の弓道で行われている遠的は60Mです。
しかも通し矢の場合は軒下で行われるために上には無論天井があります。天丼じゃありません。
その結果、遠くへ射通すために放物線を描こうにも厳しい高さの制限を受けてしまうわけです。
遠的をした人ならわかると思いますがこれは大変な作業です。
一概に通し矢といっても実はいろいろな競技があって、元服前(16歳未満)の子が行った「半堂射」(60M)の通し矢、100本中何本通るかの「百矢」、1000本中何本通るかの「千矢」などいろいろあり、その中で一番の華がいわゆる「通し矢」、24時間耐久で何本通るかを競う「大矢数」という競技だったわけです。
このために弓矢、カケも工夫に工夫され、現在でおなじみの硬帽子のカケや四つガケなどが生まれました。
100本射通すことが凄い凄いというレベルから始まり、一大ムーブメントを引き起こした通し矢は藩の名誉をかけた大勝負となり、主に尾州と紀州がしのぎを削りあって競争しました。そんな中、通し矢8000本で記録を残したのが尾州の星野勘左衛門。その後、1686年に8133本射通して天下を取ったのが皆大好き射法訓でおなじみ吉見順正の弟子である和佐大八郎だったのです。
感化されたどこぞの弓道バカが買ったマンガでは星野勘左衛門と和佐大八郎の二人は昔から勘左兄貴・大八弟みたいな関係だったらしく、先にアニキが8000本で天下を取った後、かわいいオトウトが一生懸命にアニキの記録を超えようとがんばっている姿を見て手助けをし、結果オトウトが8133本を射通し、アニキはそれに満足すると一人消えていった。と描いてありました。これが事実だとすると実にドラマチック。事実であってほしいところです。
和佐大八郎が記録を残した後、通し矢はだんだんとブームが過ぎ去っていくことになり、元服前の少年がやる半堂射が主に行われるようになっていったそうです。しかし元服前といっても侮ることなかれで、11歳~13歳の子が24時間で12000本近く射ち、ほぼ90%中てるという記録が残っているのです。
通し矢自体は戦前まで行われていたらしく、映像として通し矢を行っている姿が残っています。
さすがに現在通し矢をすることはできないでしょうがね・・。
ちなみに通し矢の競技には「継ぎ縁」という競技もあったらしく、その名の通り縁を継ぎ足して射通す距離を伸ばすという競技だったそうです。もちろん高さ制限を受けた中で距離を伸ばしていくわけですから相当な弓力と技術がなければできるものではないでしょう。これは何本通したかという競技ではなく、数ある矢のうちに一本でも射通せば記録更新になったらしいのですが、その継ぎ縁も一度やりだすとどんどん記録が伸びていってしまいには180Mを超えて三十三間堂の塀を超えないといけなくなったので不可能になり競技も中止になったそうです。
現在は和佐大八郎の記念碑(?)が河南弓道場にありますが、体育館の影にあるせいかひっそりとしていてそこのハトと同じく不遇な扱いを受けてます。記念碑といえば田辺の弓道場にもあったような気がしますが、もしかしてあっちが正真正銘の記念碑なのかもしれません。詳しいことは知りません。
和佐大八郎の本場である和歌山においても紀州竹林の射術も廃れているらしく寂しいところです。
こんな感じで現代の弓道家にとって三十三間堂関連の話題はビックリ人間コンテストとなんら変わらない歴史をもっています。ちなみに道場控えの本棚に通し矢物語である「弓道士魂」がチョコンと置いてあるはずなので一度読んでおくと賢くなれるかもしれません。
そうです、すでに時は20日を迎えており実際に遠的を行ったのは先週の話です。
三十三間堂といえば堂射、いわゆる通し矢が有名です。この通し矢のゆかりで今回の遠的大会が行われているわけですが、通し矢そのものがいったいどういったものであったのかご存知でしょうか。
通し矢というのは三十三間堂の軒下をその名の通り射通す競技であって、120Mあります。ちなみに今の弓道で行われている遠的は60Mです。
しかも通し矢の場合は軒下で行われるために上には無論天井があります。天丼じゃありません。
その結果、遠くへ射通すために放物線を描こうにも厳しい高さの制限を受けてしまうわけです。
遠的をした人ならわかると思いますがこれは大変な作業です。
一概に通し矢といっても実はいろいろな競技があって、元服前(16歳未満)の子が行った「半堂射」(60M)の通し矢、100本中何本通るかの「百矢」、1000本中何本通るかの「千矢」などいろいろあり、その中で一番の華がいわゆる「通し矢」、24時間耐久で何本通るかを競う「大矢数」という競技だったわけです。
このために弓矢、カケも工夫に工夫され、現在でおなじみの硬帽子のカケや四つガケなどが生まれました。
100本射通すことが凄い凄いというレベルから始まり、一大ムーブメントを引き起こした通し矢は藩の名誉をかけた大勝負となり、主に尾州と紀州がしのぎを削りあって競争しました。そんな中、通し矢8000本で記録を残したのが尾州の星野勘左衛門。その後、1686年に8133本射通して天下を取ったのが皆大好き射法訓でおなじみ吉見順正の弟子である和佐大八郎だったのです。
感化されたどこぞの弓道バカが買ったマンガでは星野勘左衛門と和佐大八郎の二人は昔から勘左兄貴・大八弟みたいな関係だったらしく、先にアニキが8000本で天下を取った後、かわいいオトウトが一生懸命にアニキの記録を超えようとがんばっている姿を見て手助けをし、結果オトウトが8133本を射通し、アニキはそれに満足すると一人消えていった。と描いてありました。これが事実だとすると実にドラマチック。事実であってほしいところです。
和佐大八郎が記録を残した後、通し矢はだんだんとブームが過ぎ去っていくことになり、元服前の少年がやる半堂射が主に行われるようになっていったそうです。しかし元服前といっても侮ることなかれで、11歳~13歳の子が24時間で12000本近く射ち、ほぼ90%中てるという記録が残っているのです。
通し矢自体は戦前まで行われていたらしく、映像として通し矢を行っている姿が残っています。
さすがに現在通し矢をすることはできないでしょうがね・・。
ちなみに通し矢の競技には「継ぎ縁」という競技もあったらしく、その名の通り縁を継ぎ足して射通す距離を伸ばすという競技だったそうです。もちろん高さ制限を受けた中で距離を伸ばしていくわけですから相当な弓力と技術がなければできるものではないでしょう。これは何本通したかという競技ではなく、数ある矢のうちに一本でも射通せば記録更新になったらしいのですが、その継ぎ縁も一度やりだすとどんどん記録が伸びていってしまいには180Mを超えて三十三間堂の塀を超えないといけなくなったので不可能になり競技も中止になったそうです。
現在は和佐大八郎の記念碑(?)が河南弓道場にありますが、体育館の影にあるせいかひっそりとしていてそこのハトと同じく不遇な扱いを受けてます。記念碑といえば田辺の弓道場にもあったような気がしますが、もしかしてあっちが正真正銘の記念碑なのかもしれません。詳しいことは知りません。
和佐大八郎の本場である和歌山においても紀州竹林の射術も廃れているらしく寂しいところです。
こんな感じで現代の弓道家にとって三十三間堂関連の話題はビックリ人間コンテストとなんら変わらない歴史をもっています。ちなみに道場控えの本棚に通し矢物語である「弓道士魂」がチョコンと置いてあるはずなので一度読んでおくと賢くなれるかもしれません。
Posted by 管理人 at 23:12│Comments(0)